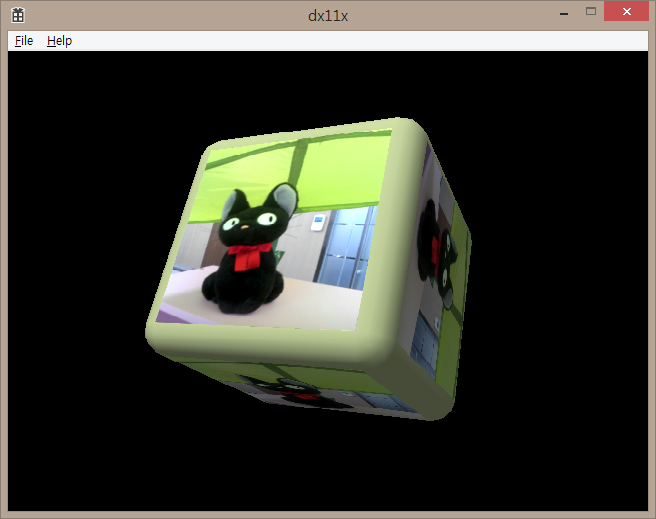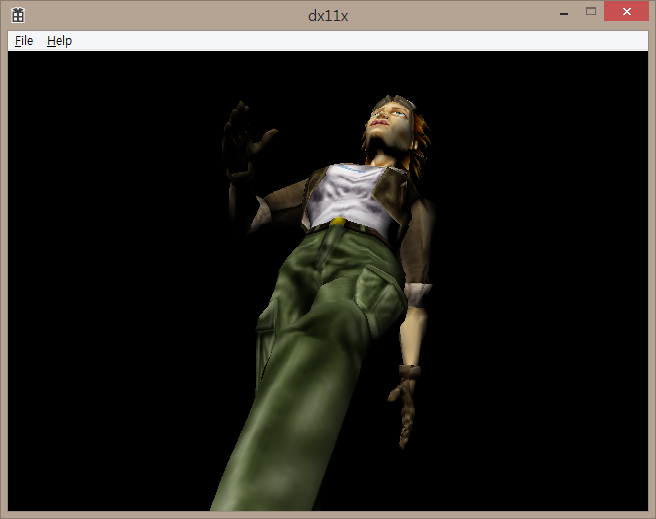今まで以下のような秒単位の時間計測関数を、Android用とWindows用にそれぞれ作って使っていました。
今更ながら、C++11のstd::chronoでどちらでも動く関数を書けることに気づき、以下のように書きなおしました。
static auto startが妙ですが、こうするとGetTimeの初回呼び出し時の時間をstartに記録できます。あとは毎回のGetTimeの呼び出しでstartからの経過時間を秒単位で返します。
#include <chrono> で "fatal error: chrono: No such file or directory"というエラーが出てしまう場合、build.gradleでgnustlを使うよう設定する必要があります。build.gradleの一部を抜粋します。
"stlport_static"ではだめで、"gnustl_static"を使う必要があるようです。android-ndk-r10d\sources\cxx-stl\stlport\stlportにはchronoが入っていないのに対し、android-ndk-r10d\sources\cxx-stl\gnu-libstdc++\4.9\includeには入っていました。